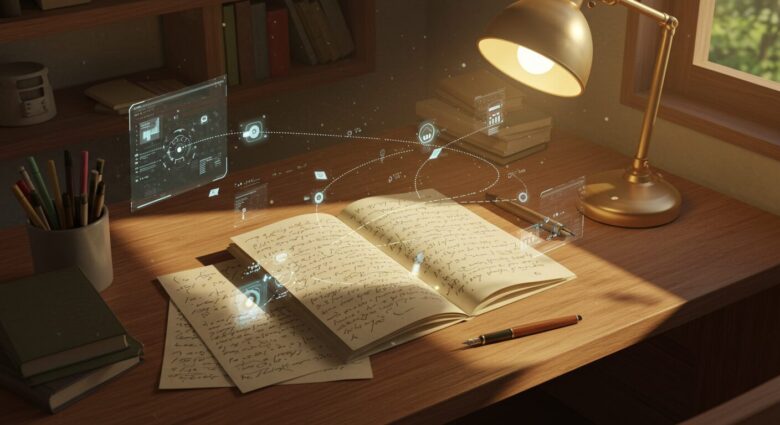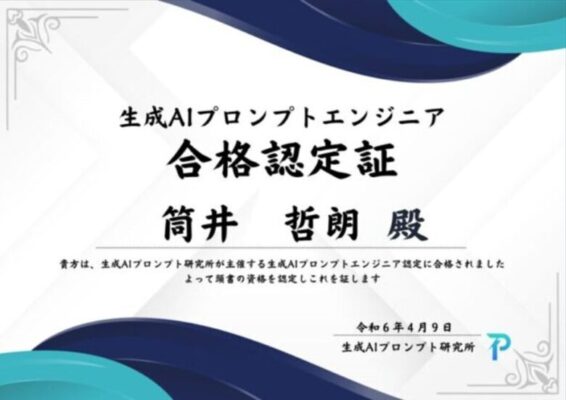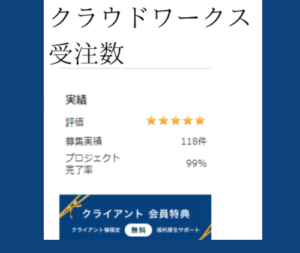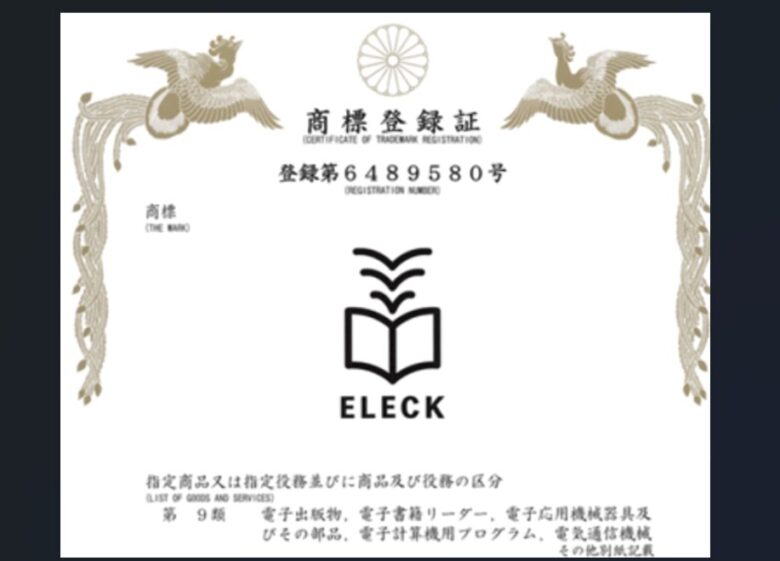STEP 3(3~4週目):設計図を作り、AIと走り出す! 目次作成&執筆トレーニング
本の骨格=目次を固め、AIをパートナーに執筆の第一歩を踏み出す!
3-1. なぜ最初に「目次(本の設計図)」を作るのか?
STEP 2では、あなたの経験というお宝から「テーマ」を発掘し、「仮タイトル」を決めましたね。
今回のSTEP 3では、いよいよ本の「中身」作りに着手します。
その最初のトレーニングが、本の「目次(もくじ)」、つまり「設計図」を作ることです。
「え?いきなり本文を書くんじゃないの?」と思うかもしれませんが、ちょっと待ってください!
設計図なしに家を建て始める人はいませんよね?本作りも同じです。
なぜ目次(設計図)が重要なのか?
- 読者のため: 目次があれば、読者は本全体の流れを把握し、「どこに何が書いてあるか」が一目で分かります。興味のある箇所から読んだり、後で読み返したりする際の道しるべになります。
- あなたのため: 目次があれば、あなた自身が「何を」「どの順番で」書けばいいのかが明確になります。執筆中に話が脱線したり、構成に悩んだりするのを防ぎ、大きなテーマを manageable(扱いやすい)な小さなパーツ(章や節)に分解することで、執筆のハードルをぐっと下げてくれます。
もちろん、ここで作る目次は「完璧な最終版」である必要はありません。
執筆を進める中で、より良い構成が思いつけば、柔軟に変更しても大丈夫です。
まずは、あなたのアイデアを整理し、読者に価値を届けるためのしっかりとした骨格(目次)を作るトレーニングから始めましょう!
3-2. トレーニング開始! AIとテンプレートで「読まれる目次」を設計する
それでは、具体的な目次作成トレーニングです!
「どうやって作ればいいの?」という方も、心配はいりません。当ジムでは、初心者でも安心の「テンプレート」と「AIトレーナー」のサポートを用意しています。
「初心者でもわかる そのまま使える!ジャンル別・目次テンプレート」を活用する
まずは、あなたのテーマに近い目次テンプレートを選んでみましょう。
基本的な構成(はじめに、本論(数章)、まとめ、おわりに等)の「型」を知ることで、ゼロから考える負担が軽くなります。
AIで目次をブラッシュアップ!
テンプレートを参考にしつつ、あなたの本のテーマやターゲット読者、伝えたいことに合わせて、AIと一緒に目次を具体化していきます。
- 目次案の生成: テーマやキーワードをAIに伝え、魅力的な章立てや見出しのアイデアを出してもらいましょう。
- 構成の整理: あなたのアイデアをAIに伝え、論理的な流れになるように章の順番を入れ替えたり、小見出しを追加・修正したりするのを手伝ってもらいます。
- 各章の内容整理: 各章で具体的にどんな内容を盛り込むべきか、ポイントを整理するのをAIにサポートしてもらいます。
《AI活用プロンプト例》
【プロンプト例:目次構成案 生成】
# 指示
あなたはベストセラーを生み出す書籍編集者です。
以下の情報に基づき、読者が読みやすく、内容を深く理解でき、読後に行動したくなるような
電子書籍の目次構成(章タイトルと各章の小見出し3つ程度)を提案してください。# 入力情報
・テーマ:[あなたの本のテーマ]
・ターゲット読者:[あなたの本のターゲット読者]
・仮タイトル:[あなたの本の仮タイトル]
・この本で最も伝えたいこと(結論):[あなたの本の核心メッセージ]# 出力形式
・第1章:[章タイトル案]
・1-1. [小見出し案]
・1-2. [小見出し案]
・1-3. [小見出し案]
・第2章:[章タイトル案]
・2-1. [小見出し案]
...(同様に数章分)...【プロンプト例:章の内容を深掘り】
電子書籍の「[第X章の章タイトル]」の章で、主に伝えたいことは「[その章で伝えたいことの要約]」です。
この章の読者への提供価値を最大化するために、盛り込むべき重要なポイントや具体的なエピソードのアイデアを5つ提案してください。
ターゲット読者は[ターゲット読者]です。
これらのワークを通じて、あなたの本の骨格となる、しっかりとした目次(設計図)を完成させましょう!
※見出し作成について、AI活用の際には、各見出しを作成し終えてから、はじめにと終わりにの章を作成する流れとなります。
AIはスレッド活用で作成することで、内容が変わっていくので、メインとなる見出しが完成してから作ることが最適となります。
3-3. いよいよ執筆開始! AIを最強の「執筆パートナー」にする方法
設計図(目次)が完成したら、いよいよ家(本文)を建てる段階、つまり執筆トレーニングのスタートです!
「ついに来たか… でもやっぱり書けるか不安…」
大丈夫です!
ここでもあなたの強力なパートナー「AI」が大活躍します。
そして、忘れないでください。ジムの鉄則「60点でOK!」の精神を!
AIを上手に活用すれば、執筆のハードルは驚くほど下がります。
【AI 執筆サポート活用メニュー】
- 下書き作成アシスト: 目次の各項目について、「こんな感じで書いて」とAIに指示すれば、たたき台となる文章を生成してくれます。真っ白なページを前に固まる時間をなくせます!
- アイデア展開サポート: 「この部分をもっと詳しく説明したい」「具体例が欲しい」といった要望に、AIがアイデアや情報を補足してくれます。
- 表現力アップアシスト: 「この言い回し、もっと分かりやすくならないかな?」「もっと面白い表現ない?」そんな時もAIが別の表現を提案してくれます。
- 読者視点チェック: 「この説明で読者は疑問に思わないかな?」とAIに問いかければ、想定される質問や、より分かりやすくするためのポイントを教えてくれることもあります。
《AI活用プロンプト例》
【プロンプト例:セクションの下書き作成】
# 指示
あなたはプロのライターです。以下の目次項目について、読者が興味を持って読み進められるような解説文を作成してください。# 入力情報
・章/小見出しタイトル:[執筆したい目次項目名]
・ターゲット読者:[設定した読者像]
・この項目で伝えたい要点:[箇条書きで3つほど]
・文体のトーン:[例:親しみやすく、励ますように / 専門的だが分かりやすく]
・文字数:[700文字程度]# 実行
上記の情報に基づき、解説文を作成してください。【プロンプト例:文章の改善提案】
以下の文章を、[ターゲット読者]にとって、もっと具体的で、かつ共感できるような表現に書き換えるためのアイデアを3つ提案してください。[改善したいあなたの文章をここに貼り付け]
【重要】AIはあくまで「アシスタント」! まる投げはNG!
AIは非常に優秀ですが、万能ではありません。AIが生成した文章をそのまま使うのではなく、以下の点を必ず守ってください。
- 必ず自分の言葉でリライト(書き直し)する: あなたの個性や熱意を込めることが重要です。
- あなたの体験談や独自の見解を加える: それがあなたの本の「オリジナリティ」になります。
- 情報の正確性を確認する(ファクトチェック): AIは時に誤った情報を生成することもあります。
- 著作権や倫理に配慮する: 他者の権利を侵害しないように注意しましょう。
AIを「壁打ち相手」「下書き係」「表現のアイデア出し係」として賢く使いこなし、あなた自身の言葉で価値あるコンテンツを創り上げていきましょう!
3-4. 執筆を加速&継続させる! デジタル筋トレ効率化テクニック
執筆は時に、地道な作業に感じることもあるかもしれません。
そこで、トレーニングをより効率的に、そして楽しく継続するためのテクニックをいくつかご紹介します!
1. 音声入力で「話すように書く」!
- キーボード入力が苦手な方や、話す方が得意な方は、スマホやPCの音声入力機能を試してみましょう。
- 驚くほど速く文章が作成できることがあります。誤字脱字は後で修正すればOK! まずは頭の中のアイデアをどんどん言葉にしてみましょう。
- (※具体的な設定方法は、補足資料で共有します)
2. 短時間集中!「ポモドーロ・テクニック」
- 「25分間だけ超集中して執筆し、5分間休憩する」というサイクルを繰り返す時間管理術です。
- 短い時間なら集中力を維持しやすく、ダラダラと作業してしまうのを防げます。「よし、次の25分だけ頑張ろう!」と思えるので、精神的なハードルも下がります。
3. 「スキマ時間」を執筆タイムに!
- まとまった時間が取れなくても諦めないでください。通勤中の電車の中、お昼休み、寝る前の10分など、1日のスキマ時間を活用しましょう。
- スマホのメモアプリや音声入力を使えば、いつでもどこでも執筆トレーニングが可能です。塵も積もれば山となります!
4. 「書く」を習慣化する!
- 毎日決まった時間に、たとえ5分でもいいので「書く」時間を作りましょう。歯磨きのように、生活の一部にしてしまうのが継続のコツです。
- 執筆場所を決めておく(例:朝食後のリビングのテーブル)のも効果的です。
5. モチベーションを維持する工夫!
- 進捗管理シート(後述)で自分の頑張りを可視化する。
- 小さな目標(例:今日は1つの章を書き終える)を達成したら自分を褒める。
- 1日15分のウォーキング運動で、頭も体もリフレッシュ
これらのテクニックを組み合わせ、あなたに合った「続けられる執筆スタイル」を見つけてください。
STEP 3 のトレーニングはここまでです!
本の設計図となる目次を作成し、AIと共に本文を書き始める第一歩を踏み出しました!
次のステップでは、いよいよ本の「顔」である表紙デザインと、出版に向けた最終準備に取り組みます!